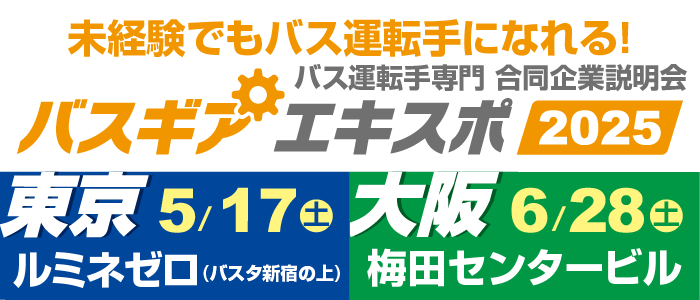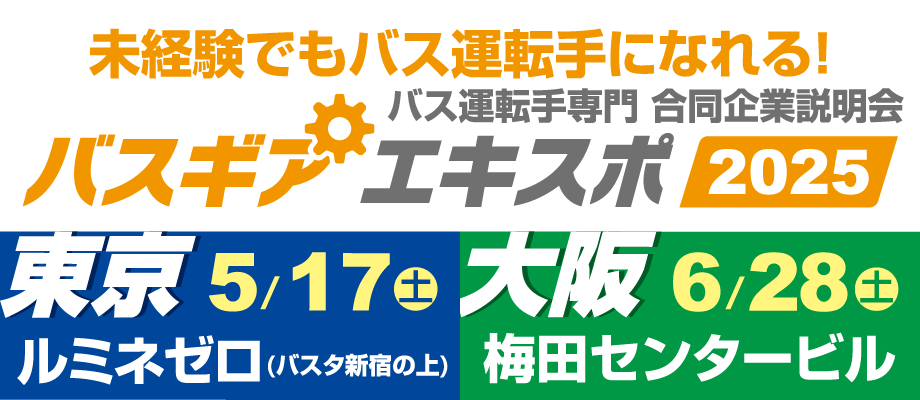さようなら、三重交通のキュービック [後編]

同社では1984年から2024年までの40年もの長きにわたって、大型路線バス「いすゞキュービック」が活躍してきましたが、ついに同社では最後の1台となる中勢営業所に所属していた1997年式のいすゞキュービックKC-LV380L、社番(三重交通での固有番号)C-1213(三重22き・977)が2024年12月をもって引退しました。
その惜別(せきべつ)記事として、三重交通最後のキュービックの姿をお伝えしますが、後編では車内を紹介するとともに、この車両が長らく活躍してきた理由、この車両への担当乗務員の思いをお伝えします。
■ 車内の前扉から中扉にかけての様子は?

それでは三重交通最後の1台となったいすゞキュービックの車内を見ていくことにしましょう!
営業運行では中扉から乗車し、前扉から降車しますが、今回は前扉から乗車して車内を見渡してみることにします。
車内は全て前向き座席で構成されており、運転席側に2人掛けの前向き座席が9席、扉側に1人掛けの前向き座席が8席並んでいます。
ツーステップ車であることから、中扉以降も最後部座席まで通路に段差はありません。
各側窓には日よけのローラーカーテンを備えています。

運転席側の座席は最前列まで2人掛けの前向き座席となっており、いわゆる郊外型の座席レイアウトです。
座席表皮のモケットは一部を除いて赤紫(あかむらさき)色系のレンガ調模様となっており、ビニール系素材でできた紺(こん)色の枕(まくら)カバーを取り付けています。

扉側の座席の様子です。
運転席側の2人掛け前向き座席と同様に赤紫色系のモケットに紺色の枕カバーを取り付けた1人掛けの前向き座席がズラリと並んでいます。
中扉直前の前向き座席は特にシートバックが高いものとなっています。

運転席側の4・5席目の2人掛け前向き座席は「善意の席」となっています。
「善意の席」とは優先席のことで、三重交通では1974年から路線バスに採用しました。
「善意の席」のモケットは灰色系レンガ調模様となっており、紺色の枕カバーには黄色の文字で表示を行っています。
■ 中扉廻りの様子は?

車内中ほどにある中扉は引戸です。
ツーステップ車であることから扉の前にステップがあります。
中扉右側には戸袋(とぶくろ)窓があります。
中扉左側は側面行先表示器があり、その下には小さな引き違い窓があります。

中扉の前側に位置する戸袋窓は、開いた中扉が収納される部分です。
この部分は開閉できず、固定窓となっています。
ここにも日よけのローラーカーテンを備えています。

中扉ステップの前側の仕切りには後付けのパンフレット入れのポケットがあります。
仕切りの後ろにある座席はシートバックが高いハイバックシートで、その次の座席はシートバックが低くなっていることが分かります。
この座席のシートバックが低い理由は整備などの際、中扉戸袋窓の車内側のガラスが点検ぶたのように車内側に開くことから干渉(かんしょう)を避けているためです。

中扉ステップの後ろ側の仕切りには整理券発行器とIC(Integrated Circuit:集積回路)カード乗車券のカードリーダーを備え付けています。
整理券発行器の色はオレンジ色のものをよく見かけますが、こちらは黄土色となっています。
■ 車内中扉以降の様子は?

中扉以降も前向き座席が整然と並んでいます。
通路も最後部座席まで段差がなくスッキリとした印象で、最後部座席部分に段差が1段あります。
つり革は扉側のみに備え付けていますが、中扉以降も乗客がよく流動するため立席(たちせき)客を考慮して最後部近くまでキッチリとあります。

中扉以降の運転席側の2人掛け前向き座席の様子ですが、右後輪タイヤハウス(タイヤの収納部分)に干渉する座席はそれをまたぐようにして設けており、タイヤハウス前側には着席した乗客の足元を水平に保つための段差があります。
ツーステップ車では出入口ステップと最後部座席廻りを除き、車内の段差はおもにタイヤハウス廻りで発生します。

中扉以降の扉側の1人掛け前向き座席の様子です。
中扉直後にある1席を除き、1人掛け前向き座席は標準のものより座面幅(ざめんはば)の広いタイプを採用していますが、中扉直後の1席は側面行先表示器の出っ張りを避け、標準的な座面幅とし、窓側にもひじ掛けを設けてます。

最後部座席は特に仕切りなどを設けておらず、5人掛けとなっています。
こちらもシートバックには枕カバーを取り付けています。

最後部座席から見た車内前方への眺めです。
ツーステップ車ならではの通路の広さと車内の開放感があり、床高の関係から乗客のアイポイントもおのずと高くなるため、車外への見通しも良い感覚を受けます。
■ 運転席廻りの様子は?

2025年現在の目から見ると少しアナログでなつかしい雰囲気のする運転席ですが、計器盤の視認性は良く、何より「OKウィンドウ」を設けていることで抜群(ばつぐん)の視野を誇ります。
計器盤の左側には、行先表示器が当初の方向幕だった時の系統設定器のスイッチやボタン類が残り、その下にはヒーターのダイヤル式のツマミがあります。
現在、行先表示器はLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)による電光式に改造されており、そのための新たな系統設定器をシフトレバー付近に設けています。
右側にあるスイッチボックス上には系統設定器のモニターがありますが、左端にある大きなモニターは、後方確認用のバックアイカメラの映像を映し出すものです。

三重交通ならではの運転席廻りの仕様として挙げられるのが運賃箱の設置位置で、一般的によく見かける路線バスの運賃箱より後ろ側に設けています。
このことによって乗務員の運転席の出入りは、運賃箱の後ろ側ではなく前側となっており、ダッシュボード真正面に手スリが設けられています。

変速機は5速MT(Manual Transmission:手動変速機)です。
床面から突き出したような長いシフトレバーの通称「棒ギア」に、この車両の歴史を感じます。

前扉と左側の「OKウィンドウ」をふくめて見た左方視界です。
非常にパノラミックで、死角を極力少なくしようとした設計であることが見て取れます。
「OKウィンドウ」はいすゞキュービックのアイデンティティであるとも言えそうです。

運転席直後の仕切りに備え付けられたのは幕式の車内案内表示器です。
スクロールによって表示内容を変えることができます。
行先表示器が方向幕の時代は、それと連動して作動させることもできたとのことで、これも三重交通ならではの仕様と言えます。
■ 長寿の秘訣(ひけつ)は乗務員さんのおかげ!?

三重交通のいすゞキュービックとしてはラスト1台となった、この1997年式KC-LV380L型の社番C-1213は、2024年12月1日に名阪近鉄旅行が主催するバスツアー商品「カッコーパルック」の「バスファン倶楽部(クラブ) 三重交通さよなら『キュービック』1213ラストラン!」で、写真撮影会をともなうバスツアーに使用された後、ついに引退しました。
三重交通にこの車両が約27年もの間、活躍し続けられた理由を尋ねたところ、3カ月ごとの法定点検を同社では2カ月ごとに行い、車両の型式に応じた同社基準の部品交換もしてきたうえで、2006年に車体再生を実施し、2016年にはエンジンのオーバーホールも行ったとのことでした。
しかし、何よりも担当乗務員の手入れが行き届いており、同型車で一番程度が良く故障も少なかったからではないかとのことでした。
同社では一部を除いて、乗務員が決まった社番の車両に乗務する担当者制を敷(し)いており、このことによって不具合の早期発見ができました。

最後にこの車両を担当していた中勢営業所の乗務員・久保 充(くぼ・みつる)さんに感想を尋ねてみました。
――27年の車歴のうち、21年間乗務させていただきました。
運転士経験の大半をこの1213とともに過ごし、この1213のおかげで無事故を続けられたと思っています。
何か気の落ち込むことがあってもスムーズに走ってくれる1213に元気をもらう日もありました。
また、全国各地から1213を見に来ていただき、多くの方とお話をさせていただくことができたことも大切な思い出です。
自分の手から離れてしまうことを今は大変さびしく感じていますが、これまでの思い出を大切にこれからも頑張っていきたいと思います。
実は引退後、本当に幸いにしてこの車両はバス愛好団体に引き取られることが決まったとのことで、この記事をご覧いただいている皆さんもまたどこかでこの車両に再開できる機会があるかもしれません。
※ 取材協力 : 三重交通株式会社
※ 写真・文 : 宇佐美健太郎
※ 協力: 鎌田 実
※ 本記事内中に公開している写真は記事制作を条件に事業者の特別な許可を得て撮影したものです。記事中の車両についてのお問い合わせを事業者へ行わないようお願い申し上げます。
この記事をシェアしよう!
フォローする
FaceBookのフォローは2018年2月で廃止となりました。
フォローの代わりにぜひ「いいね!」をご活用下さい。