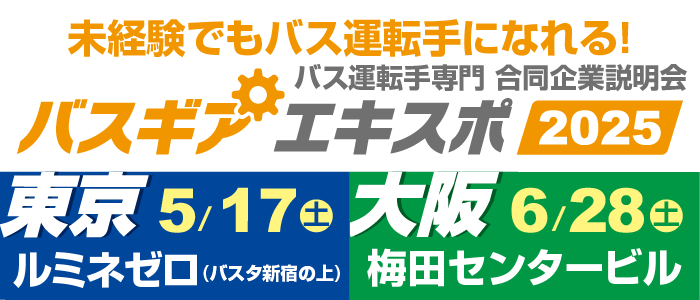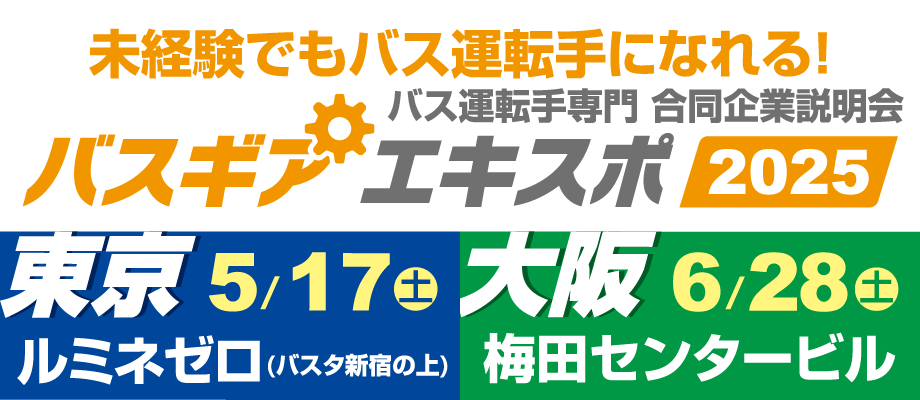実は車内が特別!? 奈良交通のBYD電気バス [後編]

奈良県に広く一般路線バス網を展開している奈良交通でも、2023年3月にBYD製小型EVノンステップ路線バスJ6(ジェイ・シックス)を2台導入して奈良市内観光路線「ぐるっとバス」で営業運行を行い、2024年2月には大型EVノンステップ路線バスのBYD K8 2.0(ケー・エイト・にーてんゼロ)を2台導入し、JR奈良駅~山村町(やまむらちょう)などの山村線で営業運行を始めました。
BYD K8 2.0は2025年2月にも2台増備し、現在、4台が活躍しています。
今回は奈良交通の大型路線バスとしては初めてとなる本格的なEVバスを『バスグラフィック』イメージガールとともに見ていきますが、後編では車内を紹介します。
実は車内に奈良交通導入車ならではの特徴があるため、それに注目しながら見ていくことにしましょう。
■ 車内前方をつぶさに見ていくと…

それでは車内に入ってみることにしましょう!
この車両の営業運行では中扉から乗車し、前扉から降車しますが、この記事では前扉から乗車し、まず車内後方を見渡してみます。
車内は全て前向き座席で構成しており、中扉までは1人掛け前向き座席のみとなっています。
側窓廻りは成型部品で仕上げられていてスッキリとした印象です。

前扉直後にある左前輪タイヤハウス(タイヤの収納部分)の上には座席を設けていません。
また、タイヤハウス前側に車輪止め掛けを取り付けており、車輪止めを収納しておくことができます。

運転席直後にある右前輪タイヤハウス上にも座席は設けておらず、備品を保管する物入れボックスがあります。
運転席との仕切りパイプにはEDSS(Emergency Driving Stop System:ドライバー異常時対応システム)の非常ボタンがあります。
運行中に万が一、乗務員が急な体調不良などで異変をきたしたところを乗客が見かけた場合、この非常ボタンを押すと車内外に音と光で異常を知らせながら自動停止制動がかかって停車します。

運転席側には折りたたみ式の1人掛け前向き座席を4席設けており、全て折りたたむと2台分の車イススペースとなります。
床面には車イス固定ベルトの取り付け金具があります。
一番手前の座席は優先席をイメージさせるピクトグラム(案内記号)を配したモケット(座席表皮)を採用しています。

扉側の前扉と中扉の間の座席は、1人掛けの前向き座席が2席のみとなっています。
優先席となっており、ピクトグラムを配した優先席モケットを採用し、側窓下にも優先席を示すステッカーを貼っています。
中扉直前の床面には反転式スロープ板を備え付けていることが分かります。
■ 奈良交通が特別に採用した中扉以降の段上げ仕様

さて、ここまで来て少しお気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが、全国各地のバス事業者で導入が始まっているBYD K8 2.0大型EVノンステップ路線バスは、通路が前方から後方まで段差のないフルフラットとなっているものの、ご覧のとおり、奈良交通が導入した車両は何だか様相が異なります。
前中扉間はノンステップエリアであることに変わりはありませんが……。

それは、奈良交通導入のBYD K8 2.0は中扉以降の通路を段上げしている特別仕様となっていることです。
通路は低めのツーステップとなっていますが、中扉以降の座席は手前を除き、通路と座席足元との間に目立った段差がないことが特徴です。
このような特別仕様にした理由を奈良交通に尋ねたところ、中扉以降の通路がフルフラットの場合、通路と座席足元との間に段差ができ、床面に対して座面が高くなると考えたため、高齢者や子どもの立ち・座りを考え、あらかじめ通路を段上げして通路と座面の間が高くならないようにしたとのことでした。
万が一、座席から転落した場合の影響を最小限に抑えたいという意図もあるとのことです。

中扉以降は段上げエリアとなっており、最後部座席手前までは2人掛け前向き座席を中心に構成しています。
座席モケットはブルー系のタータンチェック柄となっています。
中扉直後の仕切りには整理券発行器とIC(Integrated Circuit:集積回路)カード乗車券のカードリーダーを備え付けています。

中扉の段上げ以降、運転席側の座席は2列目まで2人掛け前向き座席となっています。
2列目は右後輪タイヤハウスの出っ張りを座席の脚としてうまく活用していることが分かります。

中扉の段上げ以降、扉側の座席も運転席側と同様に2列目まで2人掛け前向き座席となっています。
車内側から見ても側窓の下部コーナーが丸みを帯びていることがよく分かります。

BYD K8 2.0の座席レイアウトとして特徴的なのが後輪タイヤハウス直後の座席で、立ち・座りや通路へのアクセスを考慮してか、ここだけ1人掛け前向き座席となっていることです。
後輪タイヤハウスの丸みによって足元が不安定になることから、1人掛け前向き座席には足元がフラットになるよう踏みヅラを設けています。
また、グリップ付きの手スリも装備しています。
非常扉の前にある座席は国産メーカーの2人掛け前向き座席となっていて、万が一、非常扉を使用する際は座席を前に倒して扉の前のスペースを確保します。

もちろん、扉側にある左後輪タイヤハウス直後の座席も同様に1人掛け前向き座席となっています。
万が一の急停車の際の飛び出し防止用に、座席の前にも手スリを設けていることが特徴で、この車種以外では現在、あまり見られない作りです。
この1人掛け前向き座席は足元も広く見えるため、意外と快適かもしれません。
その後ろの座席は、メーカー仕様の2人掛け前向き座席となっています。

実は側窓下にはスマートフォンをはじめとするモバイル機器の充電を行うことができるUSB (Universal Serial Bus:データ転送経路)ポートを随所に備え付けています。
これは一例で、運転側にある右後輪タイヤハウス直後の1人掛け前向き座席付近のものです。

最後部座席は1人掛け前向き座席を5席組み合わせて独立した5人掛けとなっています。
シートバックにあるグリップもそのまま残されている格好です。
リアウィンドウ下は走行に必要な電装品を収めたスペースとなりますが、車内への張り出しのコーナー部分には、当たりを考慮し、安全のために座席と同じ柄のモケットが貼られています。

最後部座席の背後にもUSB ポートを備え付けています。
2口のタイプが3カ所にあるので、最後部座席に着席した全員が1口ずつ使用したとしてもまだ余るほどです。
■ 車内後方から前方に戻り運転席へ…

最後部座席から車内前方への眺めです。
このようにして見ると、左右後輪タイヤハウス上に座席は設けていないことが分かります。
座席は非常扉前のものや車イススペースの折りたたみ式のものを除き、シートバックとグリップが樹脂系の成型部品で一体となった構造のものがメーカー標準仕様となっています。

車内中ほどに立った位置からの前方への眺めです。
左右前輪タイヤハウス上にも座席を設けていないことが分かります。
フロントウィンドウ直上には車内案内表示器のモニターを装備しています。

運転席の様子です。
ラウンドフォルムコックピットとなっており、ボタン、スイッチ類の操作盤に角度が付けられています。
4本スポークのステアリングホイール(ハンドル)越しに見える計器盤は電光式で、EVらしく電気の流れやモーターの状態、充電残量なども表示します。
計器盤左上には停車表示灯と車イス用停車表示灯があり、その左横には車内や後方確認用のモニターを備え付けています。
右側の引き違い窓付近には系統設定器のモニターがあります。

EVには理論上変速機はありませんが、一般的なディーゼルエンジン搭載の大型バスのAT(Automatic Transmission:自動変速機)と同じ感覚で運転ができるようなセレクトボタンを設けています。
“D”(Drive:前進)、“N”(中立:Neutral)、“R”(Reverse:後退)のモードがあります。
その隣はホイールパーク式パーキングブレーキのレバーで、圧縮空気とスプリングなどの力により作動と解除を行う大型バス・トラックならではのパーキングブレーキです。
その上の操作盤にはEV特有のメイン電源スイッチや、運転席用のEDSS非常ボタンがあります。

運転席右脇のスイッチボックス上面には開閉スイッチのほか、車載音響機器メーカー・クラリオン製の音声合成放送装置の操作盤、我が国とドイツ連邦共和国の合弁メーカーであるエバスペヒャーミクニクライメットコントロールシステムズ製のプレヒーターのスイッチなどがあります。
プレヒーターとは冬期に車内を暖める装置です。

BYD K8 2.0は奈良交通としては初導入となる本格的な大型EV路線バスであるため、導入に際し、乗務員側でどのような準備を行ったのかを最後に尋ねてみました。
ディーゼルエンジン搭載の従来の大型路線バスとは異なり、EV特有の減速時の運動エネルギーを電気に変換してバッテリーに蓄(たくわ)える回生(かいせい)ブレーキの操作をはじめ、中扉アウタースライドドアの開閉操作、充電作業といったこれまでにない動きを伴うことから、この車両に乗務予定の乗務員が営業運行を行う前、営業所内で専用の教習を約1日行ったとのことです。
※ 取材協力 : 奈良交通株式会社
※ 写真・文 : 宇佐美健太郎
※ 本記事内中に公開している写真は記事制作を条件に事業者の特別な許可を得て撮影したものです。記事中の車両についてのお問い合わせを事業者へ行わないようお願い申し上げます。
この記事をシェアしよう!
フォローする
FaceBookのフォローは2018年2月で廃止となりました。
フォローの代わりにぜひ「いいね!」をご活用下さい。