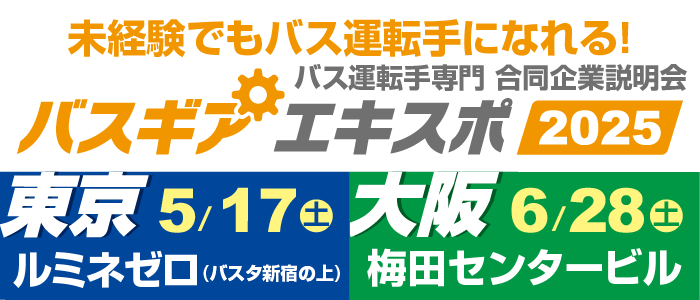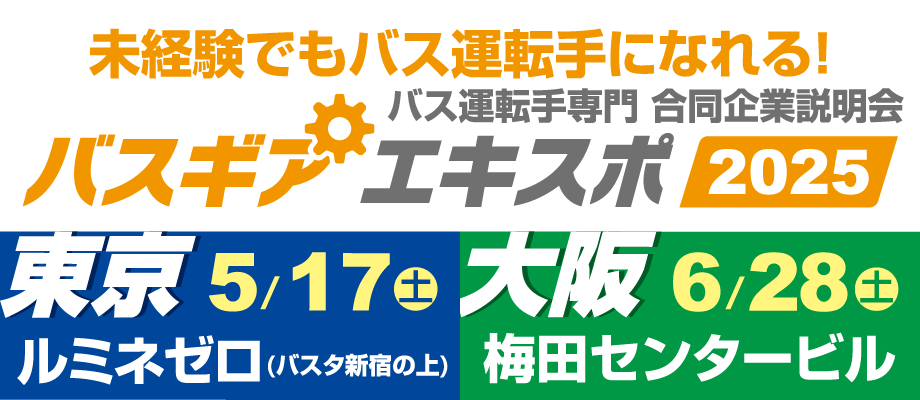さようなら、三重交通のキュービック [前編]

同社で活躍しているバスは、いすゞ自動車、日野自動車、三菱ふそうトラック・バスの3社が製造・販売した車両がほとんどを占めますが、特にいすゞの割合が高くなっています。
これは三重交通グループホールディングスのグループ企業として、三重いすゞ自動車がある関係からで、古くからいすゞの大型路線バスの活躍が目立っていました。
今回は三重交通の大型路線バスの一時代を築(きず)いたと言っても過言ではない、「いすゞキュービック」の最後の1台がついに2024年12月をもって引退したことから、その惜別(せきべつ)記事として、前後編に分け、三重交通最後のキュービックを徹底的に紹介します!
■ いすゞキュービックとは?

いすゞ自動車が製造・販売してきた大型路線バスの中に「キュービック」という車名のモデルがありました。
1984年から2000年までの間、世に送り出されており、2000年以降は「エルガ」にモデルチェンジして現在に至るため、一代限りの車名であったともいえます。
つまり現在のいすゞエルガ大型路線バスの前身モデルにあたります。

おもに路線バスとして全国各地の事業者に導入されたほか、貸切バスや自家用バス、警察の大型輸送車や健康診断車といった特装車などの用途も見られました。
路線バスでは1984年の登場からしばらくの間は、出入口に2段のステップがあるツーステップ車のみが製造・販売されていましたが、1980年代後半に路線バス低床(ていしょう)化への取り組みが活発化すると、1990年代はじめから半ばにかけてはフルフラットワンステップの試作車や改造扱いで前中扉間ワンステップ車も登場しました。

1997年からは正式に前中扉間ワンステップ車がラインナップに加わりましたが、フルフラットノンステップ車も発表され、翌年からラインナップに加わるなど、路線バスの低床化へ向けての試行錯誤(しこうさくご)とも言えるような過程が見られた時代の車種だったとも言えます。

また、いすゞキュービックは、現在に至る大型車の排出ガスによる環境問題にも本格的に取り組み出した時代の車種であり、1990年代前半から半ばにかけて環境負荷の少ないCNG(Compressed Natural Gas:圧縮天然ガス)車や蓄圧式ハイブリッド車“CHASSEÉ”(Clean Hybrid Assist System for Saving Energy:シャッセ)も登場しました。
蓄圧式ハイブリッドとは、車両がブレーキをかけた際に運動エネルギーを油圧に変えて蓄え、発進・加速時に改めて駆動力に変換して利用するメカニズムのことです。
■ いすゞキュービックの特徴とは?

いすゞキュービックは登場時、未来を予感させるような非常に斬新なデザインであると目され、バス愛好家やバス事業者を中心にして注目を集めました。
それはまず、何と言ってもこれまでの国産大型路線バスにはないようなフロントデザインにあります。

運転席からの死角となる部分を極力減らすため、「OKウィンドウ」と呼ばれる三角形をイメージさせるような視認窓をフロントウィンドウ両サイドに設けていることが大きな特徴でした。

また、フロントウィンドウも大型路線バスのほとんどが左右1枚ずつのガラスの二分割構成であることに対し、いすゞキュービックは1枚モノのガラスを使用して車内からの前方視界が大きく開けており、窓の下辺が大きくラウンドしたデザインとなっていることも特徴でした。

車体は、1980年代までの大型路線バスの主流だった外殻構造であるモノコックボディではなく、骨格構造のスケルトンボディの利点を取り入れたモノコックボディとスケルトンボディのハイブリッド構成となっていたことから、従来のモノコックボディの大型路線バスよりも車体が角張ったスタイルになったうえ、窓が大きく取れるようになったため、明快でスマートな印象を与えるものでした。
行先表示器も従来のモノコックボディの大型路線バスとは異なって大型のものとなり、後面のものはリアガラス内側に設けられたことも目新しさを与えました。

ヘッドライトは1980年代までの大型路線バスではおもに丸型のライトを採用していたため、角型4灯ヘッドライトを採用したいすゞキュービックは他の大型路線バスとは一線を画していました。

いすゞキュービックの外観のデザインは1984年の登場時から2000年の製造・販売終了まで、基本的には大きな変化はありませんでしたが、1990年と95年にマイナーチェンジを行ったことにより、リアウィンドウ廻りのデザインや側窓の構造、ホイールアーチ(タイヤ部分のボディの切り欠き)形状などが変わっているほか、1998年にはごく一部の事業者向けに特徴的だったフロントデザインを改め、写真の東武バスセントラルの車両のようにフロントガラスを二分割構成にして「OKウィンドウ」を廃止した仕様も製造・販売されました。

また、1998年から製造・販売を開始したノンステップ車は、従来のツーステップ車やワンステップ車とはそもそも車体構造が違うため、フロントデザインを除いて車体の印象は登場時のものとは大きく異なっています。
写真はいすゞキュービック・ノンステップ車の一例で奈良交通の車両です。
■ 一大勢力を築いた三重交通のキュービック

三重交通でも、いすゞキュービックは1984年の製造・販売開始時から導入が始まり、同社の路線バスの一時代を築きました。
排出ガス規制強化への適合などによるマイナーチェンジを区切りにして、いすゞキュービックは大きく分けて1984年から90年まで製造・販売された前期型、1990年から95年まで製造・販売された中期型、1995年から2000年まで製造・販売された後期型と3つに分類されます。
それぞれでホイールアーチの形状、側窓やリアウィンドウの構造など細かな部分が異なりますが、基本的な構造、デザインは終始変わりありませんでした。
今回紹介する三重交通に最後までの残ったいすゞキュービックは1997年式なので後期型に分類されます。

全長約9mの「大型ショート車」と呼ばれるタイプや大型ノンステップ車を含め、三重交通に導入されたいすゞキュービックは、前期型と中期型がそれぞれ約100台、後期型が約15台となっています。
前期型が導入された当初は写真のような新塗装が試行されました。
この車両は1984年式で、全長10.48m・ホイールベース(前後の軸距)5mの型式P-LV314L型で、津営業所に導入された社番(三重交通での固有番号)1599・登録ナンバー「三22か1529」です。
いすゞキュービックのカタログに掲載されている車両の塗装例と同じ塗り分けデザインとなっており、カタログカラーでは黄色だったところを三重交通の濃緑色としたカラーリングデザインです。
いすゞキュービックの斬新なデザインとともに、目新しさを感じさせるカラーリングデザインでしたが、すぐに従来の路線バスと同じカラーリングデザインに塗り替えられました。

今回紹介する三重交通最後のキュービックのボディは、いすゞバス製造製です。
国産大型路線バスのほとんどが別々のメーカーで製造されたエンジン・シャーシとボディを組み合わせて作られていますが、いすゞキュービックはエンジン・シャーシをいすゞが製造し、ボディは当初、川重車体工業が製造しました。
川重車体工業はその名のとおり川崎重工業系のコーチビルダー(バスボディメーカー)で、1986年にアイ・ケイ・コーチ、1995年にいすゞバス製造に社名変更しましたが、実は現在のジェイ・バスの前身にあたります。
なお、いすゞキュービックと同じ時期に製造・販売されたいすゞ製の同型エンジン・シャーシに、富士重工業製のボディを架装したタイプの大型路線バスも三重交通には大量導入されましたが、それらの外観はいすゞキュービックとは異なっています。
■ クローズアップ! 三重交通のラスト・キュービック

それでは、三重交通のラスト1台となったいすゞキュービックの外観をクローズアップしていきましょう。
型式はKC-LV380Lで、中勢(ちゅうせい)営業所に所属しています。
社番はC-1213、登録ナンバーは「三重22き・977」です。
車検証上のデータでは、初度登録年月日が1997年12月15日となっており、全長10.28m、全幅2.49m、全高3.17mでホイールベースは4.8m、乗車定員は70人となっています。
1997年当初は津営業所に導入されましたが、2005年に津営業所と鈴鹿(すずか)営業所が移転統合し、中勢営業所になったことからそのまま終生転属することなく同所で活躍し、椋本(むくもと)線、市場(いちば)線、津西(つにし)ハイタウン線を中心に津市内全般で運行されていました。

フロントガラス内側上方には現在ではほとんど見かけなくなったワンマン表示灯を備え付けています。
運転席側にはボードにより社番が掲出されていますが、よく見るとこの車両の左側面を表した線画が描かれており、「ザ★ラストキュービック」という文字も入れられていることが分かります。
また、下部の中央部分にはいすゞのエンブレムも置かれており、この車両への愛着が伝わってきます。

前扉と中扉を開いた時のステップの様子です。
ツーステップ車であるため、両者とも車体に足を掛けて乗り込んだ後、2段のステップを上がることになります。
前扉のステップは折戸開閉のスペース確保のためナナメに切り欠かれています。
路線バスにノンステップ車がかなり普及してきた現在では見かけなくなってきている構造です。

側窓は下段上昇・上段下降の2段窓、通称「サッシ窓」となっています。
いすゞキュービック後期型の側窓は2枚1組のユニット構造となっていることが、前期型および中期型と異なります。

後面の左ウィンカーとテールライトにある丸いパンチ穴は車外スピーカーです。
中扉の脇にも車外スピーカーはありますが、三重交通では後面にも装備していることが特徴です。
車外スピーカーはバス停で並んでいる乗客に案内や注意喚起を行う際に使用します。

三重交通の路線バスならではの仕様としては、リアウィンドウ上部に取り付けた2枚の車外広告枠があります。
このようなスタイルの車外広告枠を採用している事業者はあまりないことから、三重交通らしい仕様の一つであると言っても過言ではありません。

エンジンは後面にあるリッド(点検ぶた)を開けると鎮座(ちんざ)しています。
最高出力240ps(馬力)、総排気量15,200ccのV型8気筒ディーゼルエンジン8PE1-N型を搭載しています。
現在の路線バスが搭載しているディーゼルエンジンよりもパワフルなタイプです。

この車両も当然、冷房を装備していますが、一般的によく見かける屋根上の大きな出っ張りの冷房用コンデンサーのカバーはなく、床下に装備していることから、右側面に冷却用グリルを設けています。
冷房用コンデンサーは冷媒(クーラーガス)を冷やすための装備です。
車内天井にはコンデンサーより送られてきた冷媒から冷風を発生させるエバポレーター(熱交換器)を備えています。

運転席の引き違い窓の下部にも車外広告枠を取り付けています。
この部分に車外広告枠を取り付けている例もあまり多くありません。

運転席側にも右方視界を良くするための「OKウィンドウ」を設けています。
ただし、扉側のものと比較すると天地寸法が短くなっていることが特徴です。
後編では車内を詳しく紹介するとともに、この車両が長らく活躍してきた理由、この車両への担当乗務員の思いなどをお伝えします、お楽しみに!
※ 取材協力(特記以外) : 三重交通株式会社
※ 写真(特記以外)・文 : 宇佐美健太郎
※ 協力: 鎌田 実
※ 本記事内中に公開している写真は記事制作を条件に事業者の特別な許可を得て撮影したものです。記事中の車両についてのお問い合わせを事業者へ行わないようお願い申し上げます。
この記事をシェアしよう!
フォローする
FaceBookのフォローは2018年2月で廃止となりました。
フォローの代わりにぜひ「いいね!」をご活用下さい。