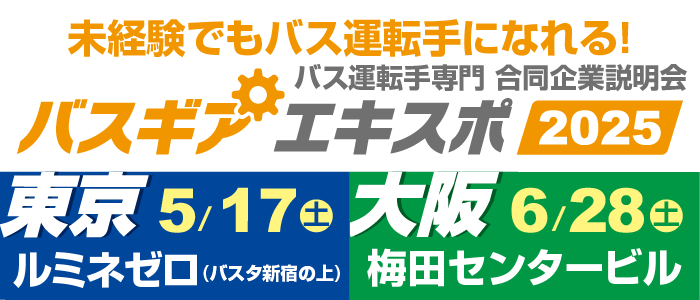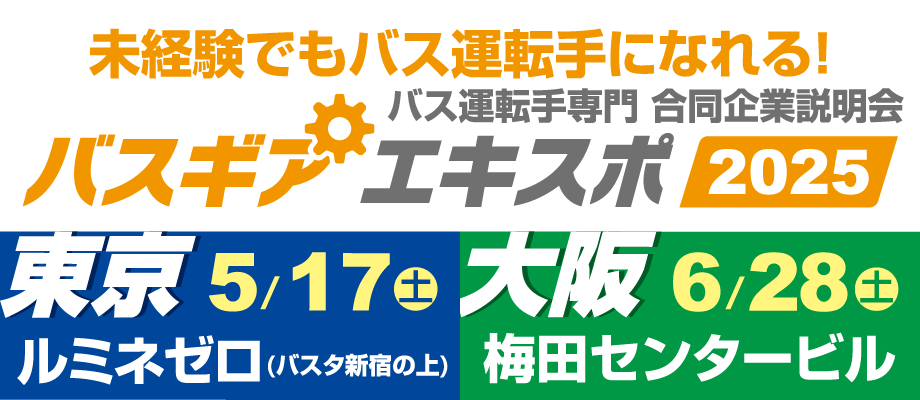実は車内が特別!? 奈良交通のBYD電気バス [前編]

一部のバス路線は京都府、大阪府、和歌山県にもおよんでおり、奈良県と各都市を結ぶ高速バス、観光バスも運行しています。
ここ2~3年の間に、全国各地のバス事業者で中華人民共和国のメーカーBYD製のEV(Electric Vehicle:電気自動車)バスの導入が相次(あいつ)いできており、2024年3月現在、登録ナンバー上ですでに200台以上の登録があるとされています。
奈良交通でも、2024年2月に大型EVノンステップ路線バスのBYD K8 2.0(ケー・エイト・にーてんゼロ)を2台導入し、さらに2025年2月には2台増備し、4台が活躍しています。
今回は奈良交通の大型路線バスとしては初めてとなる本格的なEVバスを『バスグラフィック』イメージガールとともに見ていき、前編では外観、次回の後編では車内を紹介します。
そして、実は奈良交通導入車ならではの特徴にもクローズアップしていきます。
■ 大型EVノンステップ路線バス導入の経緯とBYD選択の理由

奈良交通では、2021年12月に観光庁の支援制度を活用し、中国のアルファバス製大型EVノンステップバスECITY L10(イーシティ・エル・テン)を使用して新たな観光ルートの実証運行を行い、環境性・快適性・経済性・操作性などを検証しました。
実証運行の結果、利用者・乗務員からの評価が得られたことから、2023年3月にBYD製小型EVノンステップ路線バスJ6(ジェイ・シックス)を2台導入して奈良市内観光路線「ぐるっとバス」で営業運行を開始しました。
そして、国土交通省や奈良市の支援を受け、2024年2月にBYD製大型EVノンステップ路線バスK8 2.0を2台導入しました。
導入された2台は2024年2月26日登録の「奈良200か1344」と「奈良200か1345」で、ともに奈良営業所に所属している同型ですが、今回は「奈良200か1344」を取材しました。

奈良交通に導入する大型EV路線バスに、なぜBYD製を選んだのかを尋ねてみたところ、BYD製は2023年に小型EVノンステップ路線バスの導入実績があり、近場にBYDの事業所もあるため、万が一のトラブル時の対応も期待できるからとのことでした。
確かに、一般的に見ると少数単位で導入されるEVバスを、導入のタイミングごとに別メーカー製のものにしてしまい、複数メーカーのEVバスが混在すると管理面や整備面で不都合が生じる可能性があります。
また、BYD製大型EVノンステップ路線バスのK8は2020年から2022年まで製造・販売された1.0と、2022年にフルモデルチェンジして現在まで製造・販売されている2.0がありますが、奈良交通が大型EVノンステップ路線バスの導入を検討していた時期は、モデルチェンジ時期と重なるため、なぜ2.0を選択したのかを尋ねてみました。
すると、フルモデルチェンジした2.0が予定どおりの2022年度内の希望時期の納車でも間に合ったためとの答えでした。
■ 前面と左側面には多くのポイントが…

それでは早速、奈良交通に導入されたBYD K8 2.0大型EVノンステップ路線バスの外観を見ていくことにしましょう。
車検証上の諸元では、全長10.58m、全幅2.49m、全高3.27mで、ホイールベース(前後の軸距)は5.3m、乗車定員は80人となっています。
2020~22年に製造・販売された従来型のK8 1.0と比較すると、全長とフロントオーバーハング(前輪中心から車体前端までの距離)は変わらないものの、ホイールベールが20cm短くなり、逆にリアオーバーハング(後輪中心から車体後端までの距離)が20cm長くなっているスタイルです。
カラーリングデザインは従来の奈良交通の路線バスと同様のもので、他の事業者のようにEVバスだからと言って特別なカラーリングデザインを施(ほどこ)しているわけではありませんが、非常によく似合っていて好印象です。
特に奇(き)をてらったカラーリングデザインにしなかった理由は、奈良公園を運行する一般路線の一部に従来車とともに充当するからとのことでした。

アイボリーホワイトとグリーンの素朴(そぼく)な塗り分けながらも、精悍(せいかん)なフロントマスク。
フロントパネルには従来の路線バス同様、1946年に制定された奈良交通の社章が輝いています。
この社章は、社業である自動車運送業をイメージして円と中心に向かった3本線でステアリングホイール(ハンドル)を図案化したもので、中央には社名の頭文字である“N”をかたどったデザインを置いています。
登録ナンバーの上には、近年導入の路線バスに入れられているアルファベットの“NARA KOTSU”ロゴが配されています。
その脇に貼られている青緑色の丸いステッカーは、奈良営業所所属車を意味しています。

前面の灯火類の形状はヘッドライトやウィンカーなど全て丸型で統一されていて非常にシンプルですが、その廻りを黒色に塗っているので締まった表情に見えます。

フロントガラスは大型路線バスでよく見かける二分割のものではなく、1枚モノとなっており、前面行先表示器窓とも一体感を持たせたデザインになっています。
フロントガラスが分割されていないことから、ワイパーもいわゆる「ケンカワイパー」などと通称されているオーバーラップ型となっています。
行先表示器は白色LED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)による電光式です。

前扉は左右2枚に分かれて包み込むように開閉するグライドスライドドアです。
サイドウィンカーの横にある丸い黄色い縁取(ふちど)りの赤いボタンは非常ドアコックのボタンで、輸入車のバスの車体にはよく見られる装備です。
非常の際、このボタンを押すと手動で扉を開けることができます。
前輪ホイールアーチ(タイヤ部分のボディの切り欠き)直後には、従来車同様、奈良交通のシカのマークがあしらわれています。

前扉から2つ目の側窓上方のガラス内側に側面行先表示器を備え付けています。
こちらも白色LEDによる電光式です。
側窓には濃い着色ガラスを採用しています。

中扉も左右2枚に分かれて開閉しますが、従来の国産路線バスでは見られない構造のものなので、開いた様子は次の写真で紹介します。
中扉直後にはバス停で乗車待ちをしている乗客に乗務員が案内を行う車外スピーカーや、車外の乗客と乗務員が会話できるインターホンマイクがあります。
青い縁取りのボタンは車イスの乗客が乗車を知らせるためのボタンです。
また、中扉にも非常ドアコックのボタンがあります。
屋根肩にはEVバスをPRする「Electric Bus ―電気で走るバスです―」のロゴが書かれています。

中扉はこのように左右2枚に分かれ、外側に押し出され車体に沿って開きます。
このような構造の扉を「アウタースライドドア」と言いますが、扉が開いた際、車体側に開いた扉を収納するスペースの戸袋(とぶくろ)を設けなくても良いことから、車内を広く取れるメリットがあります。
また、扉を閉めた際には車体との段差がほとんどないため、すきま風の吹き込みが抑制されるほか、空気抵抗が低減されることから燃費向上にもつながると目(もく)されています。

中扉の床面には近年の国産ノンステップ路線バスと同じような、反転式スロープ板を備えています。
これは車イスなどの乗降の際に使用します。
上面はフラットで端に立ち上がりがないことから、周囲の端には注意喚起のためのゼブラ模様が施されています。

このBYD K8 2.0の左後輪にも、奈良交通の路線バスでは古くから採用している装備の巻き込み事故防止用タイヤカバーを装備しています。
その上の方には、EVバスをデザイン化したマークがあしらわれており、EVバスであることをさりげなく示しています。
EVバスであるため、エンジンではなくモーターで走行しますが、そのモーターは左右後輪内側にそれぞれ設けており、各々(おのおの)独立して駆動力を発揮するインホイールモーター方式となっています。
小さくても高出力の永久磁石同期モーターで、最高出力100kWのものを合計2基搭載している格好です。
■ 後面と右側面にも注目してみると…

最後に、後面にまわってから右側面も見ていくことにしましょう。
後面のリッド(点検ぶた)にもEVバスをPRするロゴとマークが大きく描かれています。
後面リッド上の右側にある小さなリッドが充電口になります。
一般的なディーゼルエンジン搭載の大型路線バスは後面リッド内にエンジンを収めていますが、EVバスであるBYD K8 2.0は、制御機器であるインバーターなどの電装品が収められています。
リアコンビネーションランプも前面の灯火類と対(つい)を成すように、丸型3連となっていて、その廻りを黒色処理しています。

リアウィンドウも1枚モノのガラスで後面行先表示器窓と一体感のあるデザインとなっていますが、窓の開口部としてはそれほど大きくはありません。
後面行先表示器も白色LEDによる電光式です。
リアウィンドウ直上には後方確認用のバックアイカメラやドライブレコーダーのカメラを取り付けています。

右側面後方には非常扉を設けています。
BYD K8 2.0は中国BYDの日本市場向けの大型EVノンステップ路線バスであることから、我が国の法令に適合した車体構造となっており、国産の大型バスと同じように右側面に非常扉があります。

右側面にはズラリと側窓が並びますが、後方のものは天地寸法が小さいタイプになっており、窓廻りを黒くすることで前方のものと連続性を持たせた処理になっています。
側窓の構造は、上段引き違い・下段固定の逆T窓で、左側面のものも同じですが、よく見ると下部コーナーが丸みを帯びたデザインになっていることが分かります。
屋根上には安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを装備し、カバーを設けているため盛り上がった形状となっています。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは車体後方床下にも分散して装備しており、トータルの容量は314kWhとなります。

運転席の引き違い窓も側窓と同じくらい大きなものとなっています。
車体右側面に描かれる奈良交通のシカのマークは右側を向いていることが分かります。

充電は奈良営業所内にある充電器で行います。
奈良営業所には充電器が2基ありますが、1基で2台分の充電をまかなえます。
奈良交通に聞いたところ、BYD K8 2.0の営業運行時間は6時頃から17時頃までの間の約10時間で、充電は入庫後、出庫までの間に行いますが、充電の所要時間は夏季で4~5時間、春季・秋季で2時間程度とのことです。
また、フル充電での走行距離はメーカーの仕様書上の数値では約240kmですが、奈良交通では夏季の電力消費を考慮し、営業運行での走行距離を1回あたりの充電で100~110km程度の仕業(しぎょう)で行っているとのことです。
営業運行はJR奈良駅~山村町(やまむらちょう)などの山村線で行っています。
後編では、いよいよ奈良交通ならではの仕様の車内を紹介します、お楽しみに!
※ 取材協力 : 奈良交通株式会社
※ 写真・文 : 宇佐美健太郎
※ 本記事内中に公開している写真は記事制作を条件に事業者の特別な許可を得て撮影したものです。記事中の車両についてのお問い合わせを事業者へ行わないようお願い申し上げます。
この記事をシェアしよう!
フォローする
FaceBookのフォローは2018年2月で廃止となりました。
フォローの代わりにぜひ「いいね!」をご活用下さい。