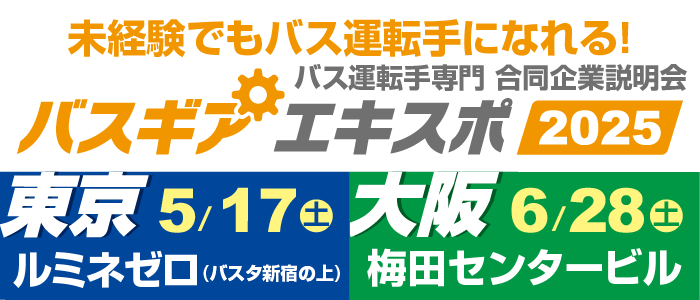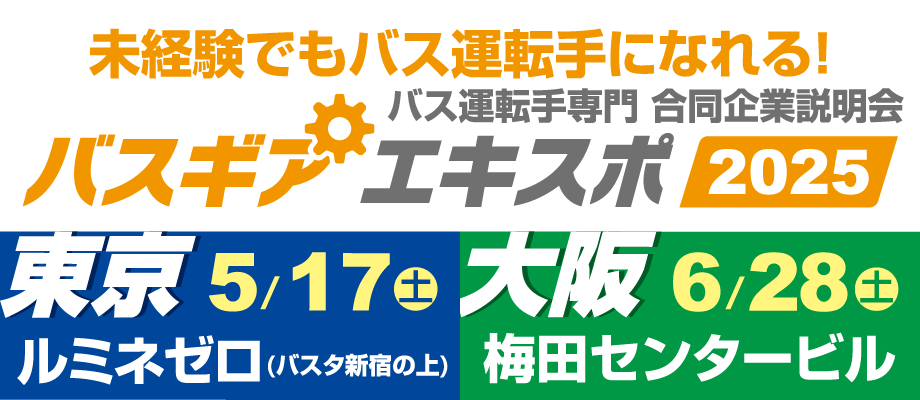世界自然遺産の屋久島へ初導入! ヒョンデEVバス“ELEC CITY TOWN”[前編]

今回は国内バス事業者へは初導入となったこのEV路線バスを前後編に分けて紹介します。
世界遺産屋久島に登場したEVバスの納車式開催

東京から飛行機で向かうと3時間ほどかかり、距離にして1,000km弱の位置にある屋久島。
手つかずの自然が残り、1993年には世界自然遺産に登録されている鹿児島県の島です。
屋久島では、いわさきグループのバス事業者の中の1社である「種子島・屋久島交通(たねがしま・やくしまこうつう)」が運行を行っています。
いわさきグループは、鹿児島県を中心にしてホテル・観光事業やエネルギー事業を展開する岩崎産業および運輸・交通事業を統括するいわさきコーポレーションを中心にして、約30社のグループ会社で構成されており、種子島・屋久島交通もそのうちの1社となります。

その種子島・屋久島交通に一挙5台ものヒョンデのEV路線バス“ELEC CITY TOWN”(エレク・シティ・タウン)が導入されることになり、2025年4月21日、屋久島いわさきホテルにおいて「Hyundai 電気バス『ELEC CITY TOWN』納車式」が開催されました。
納車式には、現代自動車グループ(HMG:Hyundai Motor Group)の張在勲(チャン・ジェフン)副会長、ヒョンデの七五三木 敏幸(しめぎ・としゆき)代表取締役社長、岩崎産業の岩崎 芳太郎(いわさき・よしたろう)代表取締役社長(取材当時・現会長)、屋久島町の荒木 耕治(あらき・こうじ)町長らが出席し、テープカットを行いました。
テープカットの後、あいさつとメディアに対しての質疑応答も行われました。
ヒョンデのEVバス“ELEC CITY TOWN”とは?

ヒョンデのEV路線バス“ELEC CITY TOWN”は2023年に登場し、2024年末から日本国内での販売を開始しました。
ヒョンデでは“ELEC CITY TOWN”をコンパクトな中型EV路線バスとして位置付けており、全長は約9mで中型バスクラスであるものの全幅は約2.5mで収容力が大きいことが特徴で、車体のサイズ感はかつて国産メーカーが製造・販売していた大型ショート車に近い印象を受けます。
カタログの諸元によると乗車定員は55人です。
前中扉間ノンステップ構造の路線バスでバリアフリーに対応していますが、観光バスとしての使用も考え、内装の質感や空調性能にもこだわっています。
EVバスならではの静粛性を備えており、屋根上にリチウムイオンバッテリーを装備し、一充電での走行距離は200km以上、充電方式はCHAdeMO(チャデモ)規格です。
EVバスであることから当然、走行時の排出ガスはなく、CO2(二酸化炭素)削減に大きく貢献します。
先進的なデザインと環境に配慮した技術を持つ次世代型バスですが、国内法規に準拠した車体規格となっており、ワンマン路線バスに必要な装備の設置に対応しています。
なぜ、屋久島にEVバスが導入されたのか?

そのような先進のEV路線バスが、なぜ種子島・屋久島交通へ導入されることになったのでしょうか?
話は昨年の2024年7月18日にさかのぼります。
同日、ヒョンデと岩崎産業との間でEVバス“ELEC CITY TOWN”5台の販売に関する基本合意書が締結されました。
いわさきグループとしては、世界自然遺産・屋久島が島全体で使用する総電力の99.6%を自然エネルギーである水力発電でまかなわれていることから、「屋久島のゼロエミッション化に尽力したい」という強い思いがあったためEVバスを導入したそうです。
また、EVバスは経済性の面でも高いポテンシャルを持っているとされ、電気代は燃料代に比べて安価で、年間の運行コストを大きく削減できることや、エンジンオイル交換や排気系部品のメンテナンスが不要になるため、整備コストやダウンタイムも低減されるというメリットがあります。

それに加えて、車両購入時に行政からの補助金が活用できることも地方のバス事業者にとっては大きいと、岩崎社長は話します。
さらに、EVバスは大容量のリチウムイオンバッテリーを装備していることから、災害時には電源車として活用でき、避難所へ電力を供給するなど、地域のレジリエンス強化に貢献できる点が評価されました。
納車式前日の2025年4月20日にはヒョンデと屋久島町の間で「屋久島における電気自動車を活用した包括連携協定」を締結しています。
なぜ、“ELEC CITY TOWN”が選ばれたのか?

近年、全国各地のバス事業者では輸入車を中心にして積極的にEVバスの導入が行われています。
EVバス導入にあたって様々な選択肢のある中で、種子島・屋久島交通へはなぜヒョンデの“ELEC CITY TOWN”が選ばれたのでしょうか。
それはすでに、いわさきグループのバス事業者でヒョンデの大型観光・高速バス「ユニバース」の導入・運行実績があったからで、岩崎社長によるとヒョンデは世界3番目の自動車メーカーで、そこがバスを作っているという信頼感があるとのこと。
現在の韓国では路線バスの70%がEVバス、10%が水素を燃料にしたバスが運行されていると言われており、そのような市場の中で発展してきたヒョンデのEVバスに関する技術力の高さ、整備性の良さ、コストパフォーマンスの高さも導入に至った理由とのことです。

本格的な導入前の2023年5月に“ELEC CITY TOWN”の試験車を屋久島へ持ち込んで、日常的に試験走行を行い、屋久島の地形や環境条件に対応できるかを検証しました。
屋久島には標高1,000m付近に広がる約270haの自然休養林「ヤクスギランド」や、標高600~1,050mに広がる屋久杉の原生林の自然休養林「白谷雲水峡(しらたにうんすいきょう)」といった観光スポットがあります。
ヤクスギランドのルートは往復約30km、白谷雲水峡のルートは往復約25kmあり、それらは急こう配、急カーブが連続する山岳ルートであるため、EVバスにとっては過酷な走行環境になりますが、“ELEC CITY TOWN”は長距離の登坂(とはん)や下り坂の制動についても問題なくクリアし、安定した走行性能が確認されました。
また、登坂時に消費される電力については、下り坂で2段階回生(かいせい)ブレーキシステムにより発電し、電力を効率良く回収できることから、エネルギー効率の面でも高く評価されました。
このことはフットブレーキの使用頻度(ひんど)の減少につながり、ブレーキ廻りの消耗品(しょうもうひん)交換サイクルの長期化が期待されるなど、運用面での大きなメリットが確認されたことも“ELEC CITY TOWN”本格導入の決め手となったようです。
“ELEC CITY TOWN”は、廃棄物を限りなくゼロにしようとする取り組みの「ゼロエミッション」にもとづいた車両で、温室効果ガス排出量を実質的にゼロにする「カーボンニュートラル」の社会を目指していくことから、岩崎社長は、従業員がそれらの一翼(いちよく)をになっているという意識が持てることも大きな意義があるとしています。
屋久島でのEVの位置付けと電力供給は?

屋久島は鹿児島県が掲(かか)げる「2050年カーボンニュートラル実現」に向けた先進地域の一つです。
屋久島での電力供給については、炭化ケイ素製造と発電事業を行う屋久島電工がになっており、島全体で使用される総電力の99.6%が水力発電で、年間の発電能力は3億kWhほどあると言われています。
なお、残りの0.4%は災害時バックアップ用の火力発電などです。
荒木町長によると、町では15~16年前から行政の補助金などを活用して公用車へのEVの導入を進めていますが、EVは災害時などにV2H (Vehicle to Home) としての役割も期待されています。
V2HとはEVのバッテリーに蓄えた電力を給電することです。
今回、種子島・屋久島交通への“ELEC CITY TOWN”納車に合わせ、ヒョンデでは屋久島町に災害時の非常用電源として活用可能なEVで、クロスオーバーSUV(Sport Utility Vehicl:スポーツタイプの多目的乗用車)のIONIQ 5(アイオニック・ファイブ)とインスターを寄贈しました。
いわさきグループでは従来のディーゼルエンジンで走行するバスを徐々(じょじょ)にEVバスに置き換えていきたいとしているほか、屋久島で行っているレンタカー事業やシェアライド事業で使用される車両もEVに置き換え、カーボンニュートラル社会の実現を目指していきたいとのことです。

ところで、現状、屋久島で水力発電により発電される電力のうち、住民生活と観光事業の利用が4分の1、残りの4分の3が炭化ケイ素や耐火物の製造に利用されています。
メディアの質疑応答に登壇(とうだん)した屋久島電工の寿恵村 哲哉(すえむら・てつや)代表取締役社長は、炭化ケイ素のおもな用途がディーゼルエンジンのDPF(Diesel Particulate Filter:黒煙除去フィルター)でのススの除去や、鉄鋼の耐火物向けに使用されることから、今後、脱炭素という中ではそういう需要は少しずつ減っていくと予想されるため、その代わりの今後の電力の使い道として、島内のEVバスやEVへの用途にシフトしていくことを期待していました。
また、将来、島内のゼロエミッションが達成したとしても水力発電での電力の供給能力は十分あまりがあるほどで問題はないそうです。
後編では、いよいよヒョンデ“ELEC CITY TOWN”そのものをクローズアップします。
※ 取材協力 : Hyundai Mobility Japan株式会社
※ 写真(特記以外)・文 : 宇佐美健太郎
この記事をシェアしよう!
フォローする
FaceBookのフォローは2018年2月で廃止となりました。
フォローの代わりにぜひ「いいね!」をご活用下さい。